歴史・沿革
日本赤十字社は、1877(明治10)年の西南戦争のさなかに設立された「博愛社」という救護団体が前身です。
日本政府のジュネーブ条約(赤十字条約)加入翌年の1887(明治20)年、博愛社は日本赤十字社に改称。
世界で19番目の赤十字社として正式に認められました。
すべての始まりは、1冊の本から。「ソルフェリーノの思い出」
スイスの実業家アンリー・デュナンは1859年、イタリア統一戦争の激戦地で放置されていた負傷者の救護活動にあたりました。その後、デュナンは当時の様子を「ソルフェリーノの思い出」に著しました。
"負傷者のための救護団体を設立できないか?"
「傷ついた兵士はもはや兵士ではない、人間である。人間同士、その尊い生命は救われなければならない」
壮大な戦争ドラマのルポルタージュである本書の呼びかけは、ヨーロッパ各国に大きな反響を呼び、デュナンは有力な仲間を得て、赤十字の誕生を実現しました。
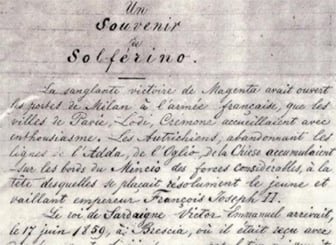 デュナンの手書き原稿(清書版)
デュナンの手書き原稿(清書版)
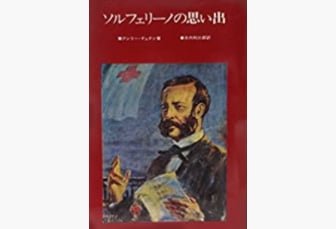 「ソルフェリーノの思い出」日本語訳
「ソルフェリーノの思い出」日本語訳
 1823(文政6)~1902(明治35)
1823(文政6)~1902(明治35)
 博愛社設立許可の図(熊本洋学校教師館ジェーンズ邸)
博愛社設立許可の図(熊本洋学校教師館ジェーンズ邸)
日本赤十字社 創立者(初代社長)佐野常民
佐野は大阪の「適塾」の緒方洪庵から医術を学び、「医は仁術なり」(身分に関係なく患者は平等に診るのだ)と教えられました。その後、1867(慶応3)年、佐賀藩士としてパリ万博の派遣団に加わり、現地で赤十字の展示を見た佐野は「敵味方の区別なく、救う」という赤十字精神に感動しました。人道精神が世界共通であることを実感した瞬間です。
1877(明治10)年2月に西南戦争が起こりました。明治政府軍と薩摩軍の激しい戦闘が繰り広げられ、両軍ともに多数の死傷者を出しました。この悲惨な状況に対し、佐野と大給恒の両元老院議官は、救護団体による戦争、紛争時の傷病兵の救護の必要性を痛感し、ヨーロッパにある赤十字と同様の救護団体を作ろうと思い立ち、奔走します。
しかし、実現には時間が掛かることがわかると、佐野は戦場で負傷する人々を一刻も早く救護したいと考えました。ついに征討総督・有栖川熾仁親王に直接、博愛社設立の趣意書を差し出すことに意を決し、同年5月、熊本の司令部に願い出ると、有栖川宮熾仁親王は英断を以て博愛社の活動を許可されました。博愛社の救護員は、直ちに現地に急行し、官薩両軍の傷病者の救護に当たりました。
1886(明治19)年に日本政府がジュネーブ条約に加入すると、博愛社は翌1887(明治20)年に日本赤十字社と改称し、現在に至ります。
年表
- 1867年
- 佐野常民 パリ万国博覧会参加(赤十字との出会い)
- 1877年
- 西南戦争の負傷者救護のため、佐野常民、大給恒が博愛社を設立
- 1886年
- 博愛社病院開設
赤十字病院のはじまり
- 1887年
- 篤志看護婦人会発足
赤十字ボランティアのはじまり
- 1887年
- 博愛社を日本赤十字社と改称
- 1888年
- 磐梯山噴火災害救護
災害救護のはじまり
- 1890年
- 看護師養成開始
看護師養成事業のはじまり
- 1890年
- トルコ軍艦エルトゥールル号の遭難事故
国際活動のはじまり
- 1894年
- 日清戦争救護(~1895年)
- 1904年
- 日露戦争救護(~1905年)
- 1912年
- 昭憲皇太后から国際赤十字に基金下賜、昭憲皇太后基金 "Empress Shoken Fund"誕生
- 1914年
- 第一次世界大戦救護(~1915年)
- 1914年
- 虚弱児童を対象にした夏季保養所開設
社会福祉事業のはじまり
- 1920年
- 日赤の看護師3人が第1回ナイチンゲール記章を受章
ポーランド孤児救済
- 1922年
- 少年赤十字誕生
青少年赤十字活動のはじまり
- 1923年
- 関東大震災救護
- 1926年
- 「衛生講習会」を開始
救急法等の講習事業のはじまり
- 1931年
- 満州事変救護
- 1934年
- 第15回赤十字国際会議(東京)
- 1937年
- 日華事変から第二次世界大戦終結までの救護活動
- 1948年
- 青少年赤十字の組織変更
赤十字奉仕団の誕生
- 1952年
- 血液銀行開設
血液事業のはじまり
- 1952年
- 「日本赤十字社法」制定
- 1959年
- 在日朝鮮人北朝鮮帰還援助(~1967年)
- 1960年
- 戦後初の医療班海外派遣(コンゴ動乱)
- 1963年
- 連盟理事会で日赤提案の「核兵器の使用、実験禁止決議」可決
- 1975年
- ベトナム難民援護事業(~1995年)
- 1977年
- 日赤創立100周年、本社新社屋完成
- 1983年
- 「NHK海外たすけあい」キャンペーン開始
- 1985年
- 群馬県「御巣鷹の尾根」の日航機墜落事故で救護班派遣
- 1995年
- 阪神・淡路大震災救護
- 1996年
- ペルー日本大使公邸人質事件で救護班派遣・活動
- 2001年
- インド大地震において初のERU(緊急対応ユニット)導入
- 2004年
- 新潟県中越地震災害救護
スマトラ島沖地震・津波災害救援
- 2005年
- 愛知万博に国際赤十字・赤新月パビリオンを出展
- 2011年
- 東日本大震災救護、復興支援(~2021年)
- 2016年
- 熊本地震災害救護
- 2018年
- 西日本豪雨災害救護
北海道胆振東部地震災害救護
- 2019年
- 東日本台風(19号)豪雨災害救護
- 2020年~
- 新型コロナウイルス感染症対応






